インターホン工事不要で取り付け方法を完全解説!DIYで簡単設置の手順とコツ
あなたは「インターホンを交換したいけど、工事が面倒で費用も心配」と思ったことはありませんか?結論、工事不要のインターホンなら電気工事の知識がなくても自分で設置できます。この記事を読むことで工事不要インターホンの選び方から具体的な取り付け手順、トラブル対処法まで完全にわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.工事不要インターホンの基礎知識と選び方

工事不要インターホンの種類と特徴
工事不要インターホンは、電気工事士の資格を持たない一般の方でも安全に設置できるインターホンです。
従来の電源直結式インターホンとは異なり、100V以上の高電圧を扱う必要がないため、感電の危険性がありません。
主な種類は以下の通りです:
• 電源コード式:親機をコンセントに差し込むだけで使用可能
• 乾電池式:親機・子機ともに乾電池で駆動
• ワイヤレス式:無線通信で親機と子機を接続
• スマートフォン連動型:Wi-Fi経由でスマホアプリと連携
これらのタイプは配線工事が不要なため、賃貸物件でも大家さんの許可を得やすく、引っ越し時の撤去も簡単です。
電源方式別の見分け方と確認ポイント
現在使用中のインターホンが工事不要で交換できるかどうかを判断するには、電源方式の確認が重要です。
DIY可能な電源方式:
• 電源コードがあり、コンセントに差し込んでいる
• 乾電池が入っている(親機または子機)
• ワイヤレスタイプで配線が見当たらない
専門業者が必要な電源方式:
• 壁から直接配線が出ている(電源直結式)
• オートロックや集合ドアホンと連動している
• 電気錠や火災報知器と連動している
見分け方のポイントは、親機の裏側や子機の内部を確認することです。
電源コードやコンセントプラグが見えれば工事不要、壁から直接配線が出ていれば工事が必要と判断できます。
ワイヤレスタイプとコード式タイプの違い
ワイヤレスタイプは、親機と子機が無線通信で接続されるため、配線工事が一切不要です。
設置場所の自由度が高く、電波の届く範囲内なら任意の場所に設置可能です。
ただし、電波の届く範囲に制限があり、建物の構造や障害物の影響を受けやすいというデメリットがあります。
コード式タイプは、親機と子機をチャイムコードで接続します。
通信の安定性が高く、電波の影響を受けにくいのが特徴です。
しかし、チャイムコードの配線が必要なため、設置場所が既存の配線に依存します。
選択の基準は、通信の安定性を重視するならコード式、設置の自由度を重視するならワイヤレス式がおすすめです。
賃貸物件での設置可能性とメリット
賃貸物件での工事不要インターホン設置は、原状回復の心配がないため非常に有効です。
従来の有線インターホンでは壁に穴を開ける必要がありましたが、工事不要タイプなら壁を傷つけることなく設置できます。
賃貸物件でのメリット:
• 大家さんの許可が得やすい
• 引っ越し時に簡単に撤去・移設可能
• 原状回復工事費用が不要
• 防犯機能を手軽に向上させられる
設置時の注意点として、両面テープや粘着テープを使用する場合は、剥がしやすいタイプを選ぶことが重要です。
また、管理会社や大家さんに事前に相談することで、トラブルを未然に防げます。
2.インターホン工事不要の取り付け方法完全ガイド

事前準備と必要な工具の確認
工事不要インターホンの取り付けには、基本的にドライバー程度の工具で十分です。
必要な工具:
• プラスドライバー(2番)
• マイナスドライバー
• 電動ドリル(壁の材質によっては必要)
• 水平器(正確な設置のため)
• 絶縁テープ(配線処理用)
事前準備のチェック項目:
• 既存インターホンの電源を必ず切る
• 設置場所の材質確認(木材、コンクリート、金属など)
• 新しいインターホンの付属品確認
• 取扱説明書の事前読み込み
安全上の注意点として、作業前には必ずブレーカーを落とし、既存のインターホンに電流が流れていないことを確認してください。
親機の設置手順と注意点
親機の設置は、正確な位置決めが最も重要です。
設置手順:
-
古い親機の取り外し
- 電源を切り、上にスライドさせて取り外す
- 配線が接続されている場合は慎重に外す
-
新しい親機の台座取り付け
- 水平器で水平を確認
- 壁の材質に応じた適切なネジを使用
- 台座の固定はしっかりと行う
-
配線の接続
- チャイムコードを適切な端子に接続
- 配線は無極性なため、どちらでも可能
- 接続後は絶縁テープで保護
注意点として、親機の高さは床から120~150cm程度が適切です。
また、直射日光の当たる場所や湿気の多い場所は避けてください。
子機の取り付け方法とコツ
子機の取り付けは、来訪者が使いやすい位置に設置することが重要です。
取り付け手順:
-
設置場所の決定
- 門扉や玄関ドア付近の見やすい位置
- 雨がかかりにくい場所を選択
- 地面から120~150cm程度の高さ
-
台座の固定
- 水平・垂直を確認してマーキング
- 壁の材質に応じたアンカーボルトを使用
- 強力な両面テープも選択肢の一つ
-
子機本体の取り付け
- 台座に子機を合わせて固定
- 配線がある場合は適切に接続
- 雨水の侵入を防ぐため隙間をコーキング
コツとして、子機の向きは来訪者の顔が映りやすい角度に調整してください。
また、夜間の視認性を考慮して、照明の位置も確認しておきましょう。
配線処理と動作確認の方法
配線処理は、安全性と美観の両方を考慮して行います。
配線処理の手順:
-
チャイムコードの取り扱い
- 直径0.65mm~0.9mmの単芯線を使用
- 被覆を剥く際は銅線を傷つけない
- 接続は確実に行い、ゆるみがないことを確認
-
配線の保護
- 露出部分は絶縁テープで保護
- 配線は壁に沿って整理
- 踏まれやすい場所は避ける
-
動作確認
- 電源を入れて基本動作をチェック
- 呼び出し音の確認
- 映像の鮮明度確認
- 通話機能のテスト
動作確認のポイントは、すべての機能を段階的にテストすることです。
問題があれば配線の接続を再確認し、必要に応じて調整してください。
スマートフォン連動型の初期設定方法
スマートフォン連動型インターホンは、Wi-Fi環境の構築が前提となります。
初期設定の流れ:
-
Wi-Fi環境の確認
- 2.4GHz帯域対応の無線ルーターが必要
- インターネット接続環境の確認
- グローバルIPアドレスの取得確認
-
専用アプリのインストール
- メーカー指定のアプリをダウンロード
- アカウント作成と初期設定
- 機器の登録と認証
-
ネットワーク設定
- インターホンをWi-Fiに接続
- 通信テストの実施
- セキュリティ設定の確認
注意点として、OSのバージョンアップに伴いアプリの対応状況が変わる可能性があります。
定期的なアップデートとサポート状況の確認を心がけてください。
3.設置後のトラブル対処とメンテナンス

よくある故障症状と自分でできる対処法
インターホンの不具合は、多くの場合、簡単なチェックで解決できます。
呼び出し音が鳴らない場合:
• 電池切れの確認と交換
• 音量設定の確認
• 電源プラグの接続確認
• 配線の接続状況チェック
映像が映らない場合:
• カメラレンズの清掃
• 明るさ・コントラスト設定の調整
• 子機の電源確認
• 配線の断線チェック
音声が聞こえない場合:
• 音量設定の確認
• スピーカーの故障チェック
• 配線の接続確認
• 内部の湿気や結露の確認
勝手に鳴る場合:
• 呼び出しボタンの清掃
• 配線の劣化チェック
• 内部の結露除去
• 電波干渉の確認
これらの対処法を試しても改善しない場合は、機器の寿命(10~15年)を迎えている可能性があります。
電池交換とメンテナンスの頻度
電池式インターホンの電池交換頻度は、使用環境や機種により異なりますが、一般的に6ヶ月~2年程度です。
電池交換のタイミング:
• 音声が小さくなった
• 映像が暗くなった
• 反応が遅くなった
• 電池切れ警告が表示された
メンテナンス頻度:
• 月1回:外観の清掃、動作確認
• 3ヶ月に1回:詳細な機能チェック
• 半年に1回:配線の点検、接続確認
• 年1回:総合的な性能チェック
清掃方法として、中性洗剤を薄めた水で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で仕上げます。
水分が内部に入らないよう注意し、アルコール系の洗剤は使用しないでください。
音声や映像の不具合解決方法
音声の不具合は、多くの場合スピーカーやマイクの問題です。
音声トラブルの解決法:
• 音量設定を最大にして確認
• 通話ボタンを長押しして応答
• 雑音がある場合は配線をチェック
• ハウリングがある場合は距離を調整
映像の不具合は、カメラや表示部の問題が考えられます。
映像トラブルの解決法:
• レンズの清掃(中性洗剤で優しく拭き取り)
• 明るさ調整(昼間と夜間で設定変更)
• 逆光対策(設置角度の調整)
• 画面設定の初期化
環境による影響として、気温差による結露や直射日光による色あせがあります。
これらは設置環境の改善により解決できる場合が多いです。
長期使用のための予防策
インターホンの寿命を延ばすためには、適切な予防保守が重要です。
環境対策:
• 直射日光を避ける設置場所の選択
• 雨水の侵入を防ぐコーキング処理
• 砂埃の多い場所では定期的な清掃
• 結露対策として通気性の確保
使用上の注意:
• 過度な力でボタンを押さない
• 清掃時は電源を切ってから実施
• 改造や分解は絶対に行わない
• 故障時は早めの対処を心がける
定期点検項目:
• 取り付け部の緩み確認
• 配線の劣化チェック
• 防水処理の状態確認
• 機能の総合テスト
これらの予防策により、10年以上の長期使用が可能になります。
4.おすすめメーカーと機種選びのポイント

パナソニック・アイホン・アイリスオーヤマの特徴比較
主要メーカーの特徴を比較表で整理しました。
| メーカー | 特徴 | 価格帯 | 保証期間 | 主力機能 |
|---|---|---|---|---|
| パナソニック | 豊富なラインナップ | 中~高価格 | 1年間 | どこでもドアホン、録画機能 |
| アイホン | 高品質・高機能 | 高価格 | 1年間 | 広角カメラ、夜間LED照明 |
| アイリスオーヤマ | コストパフォーマンス重視 | 低~中価格 | 1年間 | 自動録画、シンプル操作 |
パナソニックは、戸建て住宅向けの豊富なラインナップが特徴です。
「どこでもドアホン」シリーズは、ワイヤレス子機で2階からでも応答可能で、家族構成に応じた柔軟な使い方ができます。
アイホンは、インターホン専門メーカーとして高い技術力を持ちます。
セキュリティ機能に優れ、夜間でも鮮明な映像を撮影できるLED照明や広角レンズを搭載したモデルが人気です。
アイリスオーヤマは、コストパフォーマンスに優れた製品を提供します。
必要最小限の機能に絞ることで低価格を実現し、初めてインターホンを購入する方におすすめです。
防犯機能重視のおすすめ機種
防犯性能を重視する場合、以下の機能を搭載したモデルがおすすめです。
重要な防犯機能:
• 自動録画機能:来訪者を自動で記録
• 夜間照明:暗闇でも鮮明な映像
• 広角カメラ:広い範囲の監視が可能
• ボイスチェンジ機能:性別を判別されにくくする
おすすめの防犯重視モデル:
-
パナソニック VL-SWE210KLA
- 自動録画機能付き
- どこでもドアホン対応
- 夜間でもカラー映像
-
アイホン テレビドアホン
- 広角レンズ搭載
- LED照明で夜間対応
- 高画質モニター
-
アイリスオーヤマ TD-SM5030CT
- みはり自動録画機能
- 機械音声での代理応答
- コストパフォーマンス重視
これらの機種は、不審者の抑制効果と証拠保全の両面で効果的です。
コストパフォーマンス重視の選び方
予算を抑えながら必要な機能を確保するためのポイントを解説します。
コスパ重視の選択基準:
• 基本機能(音声通話・映像確認)に絞る
• 録画機能は必要最小限でOK
• ワイヤレス子機は不要なら省く
• 施工費を抑えるため工事不要タイプを選択
価格帯別おすすめ機種:
1万円以下:
• 音声のみのシンプルタイプ
• 基本的な映像確認機能
• 電源コード式で設置簡単
1~3万円:
• カメラ付きテレビドアホン
• 録画機能付き
• 操作性の良いモニター
3万円以上:
• 高画質カメラ搭載
• スマートフォン連動機能
• 多機能・高性能モデル
購入時の注意点として、メーカーの保証期間やアフターサービスも考慮してください。
マンション管理組合が選ぶべき高機能モデル
マンション全体での導入を検討する場合、以下の要素が重要です。
管理組合向け選択基準:
• 耐久性と信頼性の高さ
• 統一された操作性
• メンテナンスの容易さ
• 将来の拡張性
大規模導入のメリット:
• スケールメリットによる価格交渉
• 統一仕様による管理効率化
• 一括保守契約の可能性
• 居住者の満足度向上
推奨機能:
• 集合住宅対応機能:各住戸との連動
• 管理室連携機能:セキュリティ強化
• 記録機能:トラブル時の証拠保全
• スマートロック連動:利便性向上
導入時の注意点として、既存設備との互換性確認が必要です。
また、居住者への説明会や操作研修も重要な要素となります。
専門業者と連携し、長期的な運用を見据えた選択を心がけてください。
まとめ
この記事では、インターホン工事不要の取り付け方法について詳しく解説しました。重要なポイントを以下にまとめます。
• 工事不要インターホンは電源コード式・乾電池式・ワイヤレス式の3種類がある
• 電源直結式と違い、一般の方でも安全に設置できる
• 賃貸物件でも大家さんの許可を得やすく、原状回復の心配がない
• 基本的な工具(ドライバー程度)で設置可能
• 親機の設置高さは床から120~150cm程度が適切
• 定期的なメンテナンスにより10年以上の長期使用が可能
• パナソニック・アイホン・アイリスオーヤマがおすすめメーカー
• 防犯機能重視なら自動録画・夜間照明機能付きを選択
• コスパ重視なら基本機能に絞った機種で十分
工事不要インターホンは、専門知識がなくても安全に設置できる便利な製品です。この記事を参考に、あなたの住環境に最適なインターホンを選んで、快適で安全な住まいを実現してください。DIYでの設置に挑戦することで、費用を抑えながら防犯性能を向上させることができます。


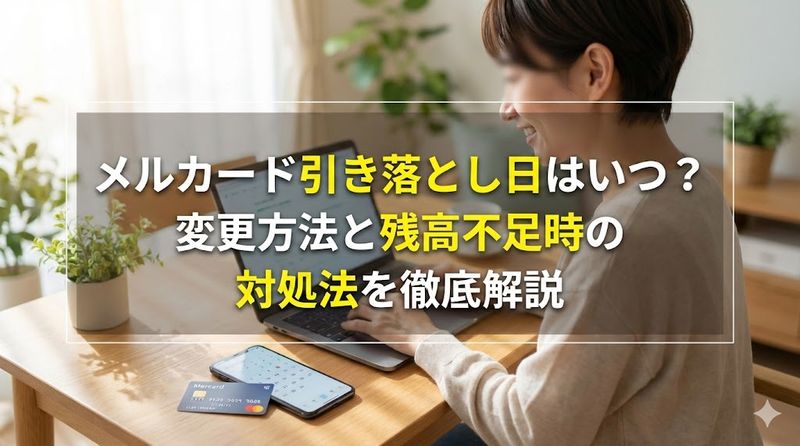
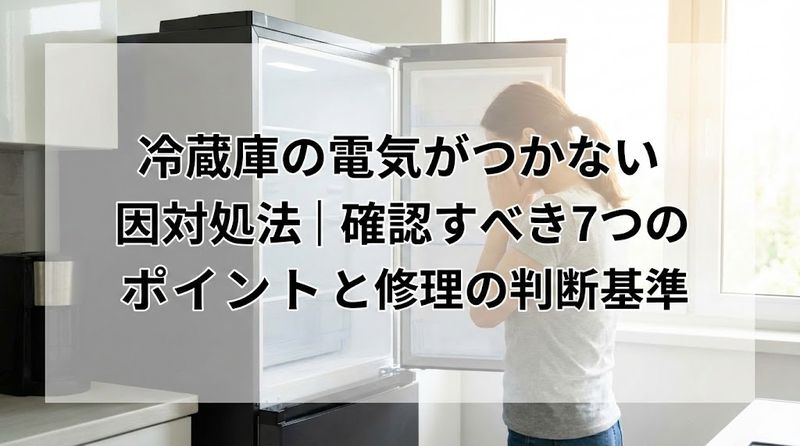
コメントを送信